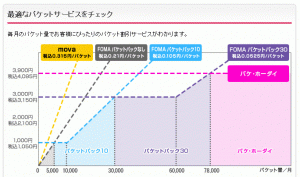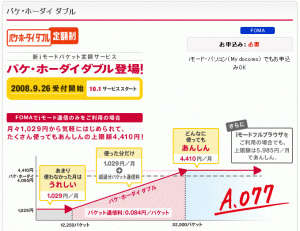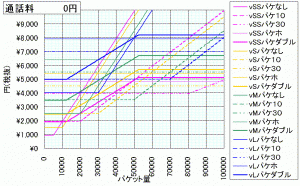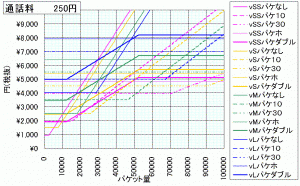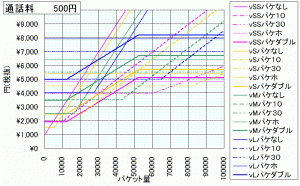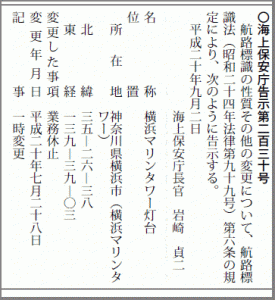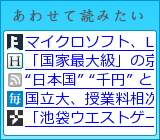2008年09月11日 木
★★★★☆
すごいいっぱいいいことが書いてあったのでほめまくりたい。
この本は、「身近に図書館がほしい福岡市民の会」という市民の会の活動記録(の2冊目)である。1冊目の「おーい図書館」が10周年の記録の本だったようで、その後の会報などからの抜粋が記録されている。
冒頭にある文章にはっとさせられた
乱読でも斜め読みでもとにかく読みあさっていると、不思議に本当のものが見えてくると思う。「眼光紙背に徹す」と、昔習った国語の先生がおっしゃった。いつの世も、まがいものが多く玉石混交して大変生きにくい世の中であるが、幼いときからたくさんの本を読んでいると、不思議とだまされないし、だまされかけても立ち直りが早いし、人間の奥行きというか、なにか立体的になるように思う。人生においてのトンネルをぬけるときのカンテラくらいにはなると断言できる。そのためにも、身近に図書館がある街にしたいと思う。
――『地域に図書館はありますか?』p.17
なんというすてきな文章ではないか。これほどまでに「図書館」のすばらしさを表現した文章に初めてであった気がする。まさにそのとおり。人生のカンテラである図書館。
中盤は、才津原哲弘さんという方の講演録。滋賀県(旧)能登川町の図書館に携わっておられたので、現在の東近江市と公演先の福岡市との比較で述べられている。
東近江市の人口は11万7千人で、6つの図書館と1つの公民館図書室があり、正規職員が25人います。福岡市東区の人口は(中略:約27万人と巻末に注あり)そこに7つの図書館があり、25人の正規職員がいると考えてみればいいのです。東区では正規職員は1人か2人くらいでしょう。
――『地域に図書館はありますか?』p.64
そうだ。横浜市もそうだが、政令市では1区に1館程度の分館があって、それで十分なような気がしているのだが、図書館の十分に行き届いた中小の都市と比較したら、ぜんぜん比べものにならないくらい足りないのだ。
本書では「中学校区1つに1館」が目安だと説いている。むむー。
横浜市で言えば人口360万人で18区あるが、1区に1館しかない。人口比でいけばなんと20万人に1館程度でしかない。東近江市と比較したら、6~7分の一というていたらくだ。
*ただし、最近気づいたのだが、横浜市は「図書館」の他に、地域公民館としての「地区センター」が区に2~3カ所あって、その中に図書室がある場合が多い。ただし、地区センター図書室は「図書館」とはまったく独立していて、有機的なつながりがない。横浜市の図書館事情を考えるに当たってはその点に留意し、地区センター図書室と図書館との連携-連合を考えたいものだ。
また、本書の中では、鳥取県の片山義博知事(当時)の講演録も入っている。この講演の中で、
実は財政難は財政難で全国財政難なんですけれども、どの団体でも必要な経費はちゃんとまかなえるように仕掛けがしてあるんです。(中略)教育だとか図書館も含めてですけれども、必要な事業に費やす標準的な財源というのはちゃんと確保されているはずなんです。(中略)我が国には地方交付税制度というのがありまして、その地方交付税制度を通じて標準的な事業、自治体にとって必要な事業はだいたいやれるように案配されているんです。
――『地域に図書館はありますか?』p.88
ああそうだ。そうだった。財政難なので図書館の経費も削減、なんてよく聞く話だが、実際は図書館用に地方交付税として与えられているお金はあるはず。それを何に(他の目的に)使うかどうかは、自治体の判断に任されているというだけなのだ。
すなわち、カネがないから、というのは理由にならない、ということだ。
(この講演録は、ディスカバー図書館 in とっとり 知事講演内容|鳥取県立図書館にもあった)
うむむー
この本。会の記録集というつくりで、全体のまとまりに欠けるきらいはあるが、現在の図書館を考えるヒントがいっぱいつまっている。いろいろなところで取り上げられるべき本だと思う。
2008年09月10日 水
★★★☆☆
先日の[post=”175″ text=”松岡正剛氏”]からのつながりで、インテリアデザイナーの内田繁の本を読んでみている。
ウツ・ウツツ・ウツロイ。のつながりは、ちょっと言葉遊びの感がなくもないが、まあ、日本文化をうまく言い表しているのかなと、思わなくもない。
あと、注連縄の「シメ」は「締める」「閉める」「占める」につながっていること。外国人(でなくてもいいけど)に日本文化を教えるときに、「注連縄のシメは、この縄を境にして、内側が神様の空間だということを意味してる~」などと話すネタになるだろうか。
この本の中で特筆すべきは、茶の湯文化の中での、茶室のしつらえの変遷がまとめられていることだ。
だが、あんまし興味なかったので軽くスルー。
もちっと生活の中でのインテリア論を読みたい気分ではある。
2008年09月09日 火
9月9日。重陽の節句。
気づいたのは、お昼ご飯を食べてるときに、wondermommyのブログを読んでから。
wondermommyの雑記帳 重陽(ちょうよう)の節句
あっ!と気づいたら、お昼に食べたのは「栗ご飯」でした。ははは。そうだったのか。写真を撮っておけば良かった。
せっかくブログにしたので、こうした日々の雑記も書きたいと思うのだが、なかなか毎日更新、とはいきませぬ。
2008年09月08日 月
★★★▲☆
世代論時代論はさまざまあるのだが、現在の30代女性を概観した論のなかで、もっとも現状をあらわしている本と言えるのではないか。
2008年09月08日 月
図書館の学校 の機関誌「あうる」
ここんところ、表紙は「図書館を使った調べ学習」に応募した子どもの写真。図書館を背景にした写真の「目」がよい。
今号は「伝える力」という特集で、かつてNHKの週刊こどもニュースで有名な池上彰氏のインタビューなど。
2008年09月08日 月
スルーしてたんだけれども、ドコモのパケット定額サービスが変わるらしい。
↓従来のパターン
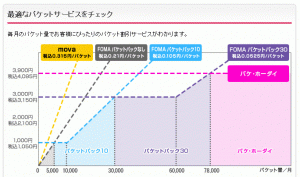
↓新しいパターン。これが始まると、従来のプランは新規受付しないとのこと。
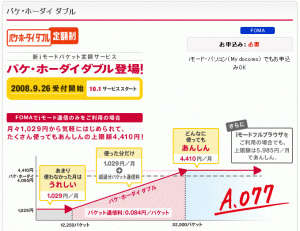
FOMAにかえてから、パケホーダイにはしていなくて、パケットパック10で十分とか思ってたんだけど、ちょっと使うと30の方がトクになったりして、しばらく使ってみてそのどちらかにしよう。などと思っていたのだが。
12月以降パケットパック10にも30にも変えられないということだ。
新プランの「パケ・ホーダイダブル」を加えてみて、金額がどうなるか調べてみた。
こういうのExcelで作るのは意外と簡単。だけど、見てもらうように体裁を整えるのは面倒で。
通話料が0円、250円、500円の3パターンについて見てみるけど、どのパターンでも、従来のパケットパックの方がやすい。
や、もっとパケットたくさん使う人は違うんだろうけれども。
新プランのキモは、無料通話分がパケットに適用されない、というところだろう。docomoも仕方なく取るところから取る方向(すなわち値上げだ)になるということか。
以下の計算がちがっていたらごめんなさい。
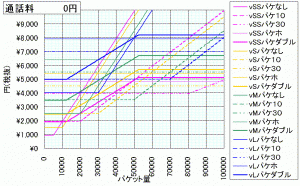
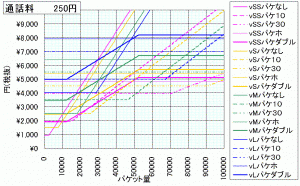
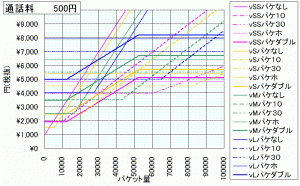
2008年09月07日 日
9月23日に、横浜線が開通して100周年を迎える。その資料展。横浜市の図書館で巡回する。
中央館での展示を見てきた。古い写真・新聞から、当時の人名録など、貴重な資料が公開されていた。一部、開港資料館などからのもあった。
うれしいのは、関連蔵書を並べて閲覧できるようになっていたこと。国鉄の古い資料とかが並べられていて、横浜市の図書館の蔵書の奥の深さを思い知らされた。
特に、市内の鉄道に関する資料は、普段はなかなか探すことができないので、こうして集められていると、次に何かの役に立ちそうだ。
郷土資料として、さまざまな古い資料が残されているのはわかっているのだが、なかなか見たりすることがなく、書庫の奥に眠っているものが多いのだろう。こうして「横浜線」というつながりで「発掘」されて日の目を見たのだなと思う。
(cache) 横浜市 教育委員会 市立図書館 横浜線開通100周年「鉄道とまちの歩み」巡回資料展
2008年09月06日 土
宮脇氏から30年後。現在の最長片道切符の記録。
関口氏のNHK放送で再注目された「最長片道切符の旅」だが、実際にスタートする人は何人かいても、実際にゴールする人はさらに少なくなるようだ。
財力や時間だけではなく、体力や気力がもっとも必要とされるということか。
往年に比べて距離は短くなったものの、こうした「旅行」ができるのは、この国ならではだろう。
2008年09月06日 土
★★★▲☆
ようやく読了。買っていたらきっと読み切れず。
驚かされるのは、文章としてメモを残していることだ。ちゃんと読める。
私だったら、項目だけを書いておいて、少なくとも体言止めにしてしまうだろうと思う。
もしかしたら作家デビュー第一作を意識して、実際に書く文章までを意識していたのだろうか。
メモと本文を対比させると、表現の変化がおもしろい。
また、旅の後半になっても、同じだけの分量がかかれていることだ。飽きてきたり慣れてきたら、略して書いたり、はぶいてしまったりするところだが、それがない。前半も後半も1日分がちゃんとした分量なのだ。
車中にあって、車窓を見つつ、時刻表を見つつ。またガイドブックなども見ながら、このノートにメモをとっていたのだろうか。
本書が刊行された当時は、ただの旅行記ではあった。がしかし、この取材ノートとともに読み返してみれば、昭和53年末時代の鉄道史実としても貴重な記録であることがわかる。電化区間と非電化区間。走っている特急列車、急行列車。水害から復旧した区間。紀勢線で振子列車が走り始めた年。新幹線が半日運休した日(今でこそ実施して総点検すべき、ではあるが、当時はまだ代替路線が機能していたが、今は望むべくもないか)。
それだけでなく、30年前の我が国の風物風土の記録としても十分なものとなっている。今はない北海道の各線に、どんな人が乗っていたのか。地方都市発の早朝の「急行」列車には、陳情などで首都へ向かう役人やビジネスマンが乗っている。どの地域にも柿の朱い実が生っていて、干し柿がつるされている。大根が干してある。日本の「国樹」は柿、「国菜」は大根との記述もある。
宮脇氏が逝って5年が過ぎた。氏の書物はいよいよ、文学の、鉄道史の、テキストとして見いだされ始めようとしているのだろう。
2008年09月05日 金
★★★▲☆
シリーズ第4巻は「読書」を中心に構成されている。
目次はこちらから
読書活動については、昨今はやりの全校一斉読書(学校で時間を決めて、その時間は全員読書しましょう。という活動)の調査結果が転載されている。
全校一斉読書によって、「本を読むのがきらいになった」という声もないわけではないこと。それから、傑作なのは、学校での活動なのに「先生と本の話をすることが多くなった」という回答が著しく低いという結果。結局は、「本を読む時間」を設けただけで、なんら「教育活動」がなされていないのだろう。
学校の先生が、「教える」という活動から実は離れていっているという実態については、またどこかで考えてみたいと思うが。
読書以外にも、出版産業の構造変化や、出版社からの意見もいくつか載せられている。
最後の章は、文字・活字文化推進機構理事長の肥田美代子氏が書いている。子ども読書年の国会決議。子どもの読書活動推進法。文字・活字文化振興法など、氏が関わった一連の活動についてまとめられている。
2008年09月05日 金
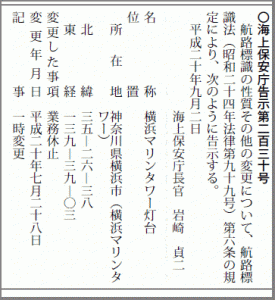
9月1日付けをもって、横浜マリンタワーが灯台でなくなった。
「灯台」とはなんぞや、ということになるが、航路標識法に基づいて「航路標識」として海上保安庁の許可を得て設置したものである。
高さ106メートルに設置された灯台としての明かりは、地上高が世界一ということでギネスブックにも記録されていたが、このほどの横浜市への譲渡と、市による「マリンタワー再生事業」に基づいて改装されている。
その中で、灯台としての役割を終えたとして、7月28日に終了。9月1日に正式に廃止となったものである。
航路標識法に基づいて、7月28日に業務休止になった旨の告示が、9月2日にあった。
第三管区海上保安本部の水路通報においては、すでに灯台の廃止が通知されている。
地上高「世界最高」の横浜マリンタワー灯台が半世紀の歴史に幕 – ヨコハマ経済新聞
開港150周年記念事業「横浜マリンタワー」整備状況について - 横浜市経済観光局 記者発表
2008年462項 水路通報詳細
2008年706項 水路通報詳細
2008年844項 水路通報詳細
2008年934項 水路通報詳細
[post=”391″]
2008年09月03日 水
★★★▲☆
「課題解決型」サービスってなにか。図書館が提供する中で、特定の「課題」に的を絞ってサービスを提供しようとするはたらきのことだ。ちょっとまえから「ビジネス支援」とか言われているけれど、そうした特定の課題がいろいろと登場している。
本書の目次から、列挙してみると、
- 仕事や生活に役に立つと認知される図書館
- 青年・女性のキャリアアップと就労支援、ニート支援
- 仕事と暮らしに役立つ図書館
- 公共図書館での健康情報サービスの発展
- 食育
- 学校図書館と公共図書館
- 法律情報の提供サービス
- 行政支援サービス
- 地域文化
- 地域情報
などとなっている。どれも今日的な「課題」である。
2008年09月02日 火
★★★▲☆
「千夜千冊」で有名な編集者。松岡正剛氏の本は初めて読んだ。
ページを繰るたびに考えさせられることが多く、なかなか読み切れずようやく読了。
日本の特徴、というか日本という「ありよう」は、その方法そのものだというはなし。