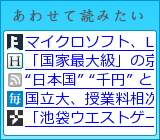2008年10月03日 金
#156 第一級殺人弁護 [書店]

中嶋博行の本はいくつか読んだような気がしていましたが、全然未読でした。
fmyokohamaの朝の番組「morning steps」。北村浩子さんのBOOKS A to Zで紹介されていたので思い出した次第。それにしても、(隔週とはいえ)毎日1冊しっかりと本を紹介する北村さんはすごい。
番組紹介 | BOOKS A to Z 2008.1-6 | Fmyokohama 84.7
2008年10月03日 金

中嶋博行の本はいくつか読んだような気がしていましたが、全然未読でした。
fmyokohamaの朝の番組「morning steps」。北村浩子さんのBOOKS A to Zで紹介されていたので思い出した次第。それにしても、(隔週とはいえ)毎日1冊しっかりと本を紹介する北村さんはすごい。
番組紹介 | BOOKS A to Z 2008.1-6 | Fmyokohama 84.7
2008年10月02日 木

★★★☆☆
水族館の数々の著作で知られる中村元氏の著。八景島シーパラダイスの現役ドルフィントレーナーである福田智己さんの視点を通して、ショートレーナーという仕事を余すところ無く伝えている。数多くの写真もかわいい。
構成は小学生~中学生向きなので、将来こうした仕事を目指す人には読みやすい。内容は大人向けにも十分。
水族館ってすげーよな
2008年10月01日 水

★★★▲☆
山根一眞氏の「袋ファイル」(86年)信奉者だった私には、野口先生の「超」整理法(93年11月)~押し出しファイリングは、それまでの延長でもあり、かつ、画期的な方針転換だった。
『「超」整理法』は、これまでの「分類する」をいっさい廃止した方法なので、「超」をつけたのだが、「チョーむかつく」という流行語とあいまって、以降の「超○○」の先鞭となった。
それから15年
本書には、あのかつて読んだ際の「目新しさ」はないのだが、それはとりもなおさず、PCが画期的に情報処理を担い、整理法への渇望感が薄れているからにほかならないだろう。とはいえ、こうした時代だからこそ、新たな整理法を必要とするのは言うまでもない。
gmailかぁ
2008年09月28日 日

★★★☆☆
依存症って難しい。ひとたびはまってしまったら、すっぱり絶つしか道がない。そうしない道はないものか。毎日飲み続けるのはよくないが、絶つのも難しい。そうした模索を自ら体験しつつ、周辺を書いた。
2008年09月24日 水

★★★☆☆
書名はややミスリード。中身は認知錯覚を中心に、人間が実際に関知理解するのは、現実と差異があるという話。時間認知にしてもそのとおりなので、どうやって社会・生活と合わせるかということだ。
2008年09月21日 日

これまで、『かながわのバスマップ』として刊行されていたのが、今回からこの版で出ることになった。
『かながわのバスマップ』は神奈川県バス協会発行で、昭文社から出ていた。これまで5版でており、
92年3月版(91年7月現在)、96年1月改訂版(95年10月現在)、2000年3月版(99年11月現在)、03年6月第4版(03年4月現在)、06年4月5版(06年1月現在)、がある。B5版、最後の刊だけA4版だった。
昭文社から人文社にかわって、大きさも小さくなった。見やすいかどうかは・・・。全停留所一覧が無くなったのが残念。
あと、系統番号がない江ノ電バスの路線に便宜上番号を振っているので、このバスマップ掲載の番号が、事実上の呼称として機能していたのだが、発行元が変わって振り直されてしまったのが、今後の路線改編を追うのに支障がないことを願う。
規制緩和~子会社化~市バスの移管化など、激動のバス路線はなかなか紙媒体では追い切れないので致し方ないが、いろんな会社が運行しているので、とてもWebサイトでは見切れない。こうした一覧図が定期的に刊行されることが望まれる。
神奈川県内乗合バス・ルートあんない No.1(’08~’09)
東京都内乗合バス・ルートあんない No.15(’08~’09)
2008年09月20日 土

定期購読してるので、今日届いていました。
今号は「東京」。
東京の地下鉄と、都電全路線が載っています。都電と地下鉄の改廃(すべての停留所)が掲載されているので、これ1冊だけ買うっていうのもありですね。
日本鉄道旅行地図帳 5号 東京 新潮「旅」ムック 全線・全駅・全廃線
c.f.・[post=”165″]・[post=”225″]
2008年09月20日 土

★★★☆☆
丸田祥三氏の写真集。市電・都電を中心に、廃車となった車両が街中に置かれ、そして棄てられていっている様子を、これでもかと多く写真に納められている。
文章にあるのは、写真を撮って歩いた際に「なぜそんな古いものに目を向けるのか」という声があったとのこと。昭和の古い時代のことを、懐かしく思い出せるのはこの時代だからであり、当時は掃き捨てるべき過去だった、という時期があった。
2008年09月18日 木

1971年11月同友館刊の再刊。もういちどいまいちど宮本常一を読み直すシリーズが刊行されている。
40年代の武蔵野地域の写真をはじめ、風土、農具などの民具、お祭りなどが記録されている。
武蔵野地域は、短冊状の耕地が特徴。現在も縦長の道路区割りが多く見られる。それからケヤキの大木も特徴。100年も200年もたつ大木が多くあったようだ。そのうちの多くが40年代以降急速に切られていってしまったらしい。
2008年09月16日 火

★★★★☆
開戦前、日本本土には約7000万の人口がいたが、本土の国土では約5000万人分のコメしかとれなかった。足りない分は朝鮮半島から補い、朝鮮半島の人民は満州でとれた粟を主食としていた。
この事実だけでも、気づかされなかったことなのだが、こうした「食料の事実」を積み重ねて、この国がどういう機序で戦争に突入することになったのかを解き明かす。
もちろん、今では、農業技術の進歩(農薬と機械化)が進んだので、5000万人分のコメしかとれないわけではなかろうが、基本的にこの国の国土全部で、この国の人口を糊することはできないのだ。
*このことからしても、食糧自給率をあげようという流れは考えたいものだ。→参考[post=”112″]
我が国は、なにか(いまは工業製品?クルマ?これからは?サービス?!?)を売って、他国から食料を買わなければならないし、そうしているからこそ今の豊かさがあるのだ。
(開戦前はブロック経済に阻まれて輸出が思うようにいかなかった背景がある。そういう意味では、貿易政策がこの国の最重要課題なのだ。実は)
平和を創り出す人は幸いである。との言葉は唱えるだけでは意味をなさない。こうして過去の事実をしっかりと解き明かし、広く理解し、明日の指針につなげていかなければならない。
2008年09月13日 土

『数学でつまずくのはなぜか』を書かれた小島寛之氏の本。
統計学は、部分から全体を推計する、のと、現在から未来を推計する、の二つの部分がまざっている。というか、前者の理論を後者に応用している。というのだ。そうだな、というか、そうだったな。昔どこかでさわったような気がする。確かに。
標準偏差は大事だ。何事においても。