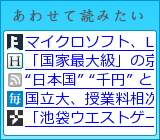2010年03月18日 木
#034 廃墟建築士 [図]

★★★▲☆
三崎亜記著
この作家の作品は、いずれも虚構だが、現実と対比できる細部が書かれていてリアリティが高い。
中に、「図書館」という掌編がある。
古代から書籍という「野獣」を封じ込めている図書館。現在は飼い慣らされて「美術館」や「博物館」と同じ地位に甘んじている。その野獣を解き放つ「夜間図書館」。
「図書館専門派遣会社」という記述があるが、そろそろ一般的になってきているということだろうか。
2010年03月18日 木

★★★▲☆
三崎亜記著
この作家の作品は、いずれも虚構だが、現実と対比できる細部が書かれていてリアリティが高い。
中に、「図書館」という掌編がある。
古代から書籍という「野獣」を封じ込めている図書館。現在は飼い慣らされて「美術館」や「博物館」と同じ地位に甘んじている。その野獣を解き放つ「夜間図書館」。
「図書館専門派遣会社」という記述があるが、そろそろ一般的になってきているということだろうか。
2010年03月17日 水

★★★★☆
袰岩奈々著
大事な本。子どもから小学生まで、おおよそ、行動の背景にある「感情」についてなかなか自覚できていないものだ。その感情についてといかけ、自身の感情に気づかせ、そして行動をとる。また、相手がどういう感情になるのか、に気づかせる。
子ども中心にそういう役割を果たされているのだろうが、実はどうして、大人にも充分にトレーニングが必要なことだ。
できれば、私たち大人に向けても、こうした「感情」を把握するトレーニングを教えていただけないだろうか。
2010年03月16日 火

★★☆☆☆
阿部紘久著
本屋でぱらぱら見た時は、役に立つことが書いてありそうに思ったのだが、実際に開いてみたらたいしたことがなかった。把握していることばかり、という感じ。入門書としてはよいだろう。だが、文法的な裏付けもとぼしく(いやまあ日本語文法そのものの問題でしょうが)、大事な時にその文法を持ち出すのがちょっと残念。
また、自分の文章感覚とちょっと違うところもあり。
「てにおは」だけではなく、長い文章の表現方法について、もう少し裂いて欲しかった、というのが私の期待。
2010年03月12日 金

★★★☆☆
矢作俊彦著
横浜が舞台の小説。二村刑事の第2弾。
「太陽の季節」みたいな時代を想像するが、2000年代が舞台らしい。
磯子のプリンスの山で、雉子が捕れたという話があった。
2010年03月11日 木

★★★★☆
島田裕巳著
宗教学者、とくにこの国の新宗教に詳しい島田氏が、宗教的な側面からこの国の現在の「葬式」について語る。
中でも特に「戒名」についての記述に多く裂いている。本来は檀家が支えていた仏教寺院だが、都市化によってその支えを失いつつあるため、葬式と戒名(代)によって支えている構造を明らかにしている。
そして「直葬」の普及。ブームというよりかは、もう普及と言ってもよいぐらいだろうか。
この国。いろいろなものが旧いままで変わっていない部分が多い。変えよう変えようという声が大きくても、なかなか変わらない。
しかし、この、葬式意識の変わりっぷりはどうか。(ついでに言うと、結婚式もそうか)
ここ数十年であっという間に、「家」という概念から、「個人」という概念にシフトしている。
大きく式を挙げるから、個人で、ちいさく、最低限に変化しつつある。
この急激な変化に文化的なものに対する影響を考えなくもないが、これはこれでよい「選択」の結果なんだろうと思う。
2010年03月02日 火

小林 弘人著
★★☆☆☆
あちこちで取り上げられている話題の本。ようやく読了。
とはいえ、なんか目新しいことがあったようには思えない。
2010年03月02日 火

西村 健太郎著
★★▲☆☆
さよなら運転に乗りに行きたくなる。で強行軍で(家族を措いて)行ってしまう。
ありし日の北海道の路線網に思いをはせる。
うーん。自分とはまったく相容れないところが多いのだが、まあ、なんとなく30~40代の鉄道ファンの標準像的な様相ではなかろうか。
2010年02月26日 金

小浜逸郎著
★★★▲☆
小浜先生の近著。いくら世の中が情報化になっても、いや情報化社会になればなるほど、人は人とのつながりを求めて動く。そういうものだ。という諦念。
2010年02月23日 火

福井 健策著
この著者の新刊を手に入れたのだが、どこかのブログで(どこだか忘れた)、前著も読むと良いようなことがあった。確か読んだはずと思ったが、手許にないので、借りて読みなおす。
以前は06年10月に読んでいた。→2006年10月2日 Mon #148 著作権とは何か
2010年02月22日 月

真藤 順丈著
★★★☆☆
棚落ちしていたので取ってみる。期待したほどではなかった。
塩浜の南海橋の近くの路上に、東京23区を図形化した陶板が埋め込まれたところがあるらしい。
2010年02月19日 金

竹沢 尚一郎著
★★★▲☆
人々が「社会」というものを意識しだし、それを国家観に結び付けていった系譜。
中世のヨーロッパにあっては、封建主義から啓蒙主義へと発展していった訳だが、そのなかにあって、グーテンベルグの印刷技術が興ったこと契機になっていたのはいうまでもない。それに加えて、本書では、「百科全書」の効用も挙げられている。知を包括する試み。それが公共意識を生み出す流れと相まっていたという。
逆に、印刷メディアの歴史や価値をを考える際には、本書にあるような「社会観」(すなわち国家観・世界観)の変遷をもあわせて見なければならないだろう。
先日「図書と図書館史」の単位をとったばかりだが、図書館の歴史を考える上で、17世紀のこの「百科全書」の位置づけは、なかなか取り上げられていないのではなかろうか。
知の総合目録を確立し、啓蒙主義の扉を開いたことが明らかにされているわけだが、これがデューイの分類学につながっていることは明らかだ。
(図書館の十進)分類を考えてみると、その体系を網羅する難しさにふれたわけだが、総ての知を網羅し体系的に位置づけるという作業は、この「百科全書」に端を発しているといえよう。
もう少し図書館学の分野、なかでも目録・分類の歴史という中で、この「百科全書」は取り上げられても良いのではなかろうか。
また、「図書館史」全体のなかにも、もうすこしこうした「社会観」の歴史も踏まえられるとよいなあと思う。昨今の「活字文化」(?私にとってはなにそれ?、だが)とか、「出版文化」を声高に叫ぶ人には、こうした「社会観」の歴史も踏まえて語ってほしいものだ。
2010年02月18日 木

江上 剛著
★★★☆☆
過労死なのか自殺なのか。労災訴訟を扱ったストーリー。
奥深さは全然なくするっと読了。雑誌連載だったか。
重要なテーマだが、さらっと読める。簡単に人を引き付けておいて、ざっと知識の概観を提示する。こんなようにさらっと扱うのも、経済関係の小説を多く書くこの著者にとっては、いい仕事と言えるだろう。