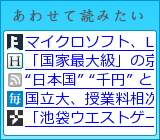2008年12月21日 日
#200 時の“風”に吹かれて 光文社文庫 [書店]

★★☆☆☆
梶尾真治の短編集。まあまあ。
2008年12月17日 水

★★★★▲
小説を読む、ということは、人間を読む、ということだ。人間って、人ってなんだ。こころのうちに秘めるものはなにか。
さいしょからどろどろとしていて、ばらばらに出てくる3人がすれ違い、そして下巻へ続く。
2008年12月15日 月

2007年に亡くなられた筑摩書房の物流担当だった田中達治氏によるコラム集。出版社の中から特に物流関連の話題が多く取り上げられており、そういう意味で出版界に資するところありということで、ポット出版から本になったもの。
2008年12月12日 金

★★★▲☆
ちょっと厚くて冗長な部分も多いが、交通とくに自動車交通の「心理的」側面による最近の知見がおおく盛り込まれている。
道路交通情報で渋滞の情報を流すが、もし、それがすべての人に伝達でき意思判断をせまることになったら、その時点で渋滞は発生しなくなり、情報が変わってしまう。
人間という集合をコントロールするむずかしさ。それにはさらに、反射時間の遅れとか、行動選択のゆがみとか、人間の持つ人間的な能力の特質もかかわる。
というはなし。
このまえ読んだ、自転車の本(c.f.[post=599])を読んでも思ったが、学生の頃はなかなか研究するに足る「交通の問題」を見つけられなかった。十数年経った今、まだまだ解決すべき課題も多いし、研究としてとりあげられるに足るテーマにあふれているのをおもう。自動車を運転するようになったり、少しは広い目で見られるようになっているからこそだし、当時の不明を恥じるばかりだが、こればかりはいかんともしがたい。
2008年12月08日 月

★★▲☆☆
もとJTBの編集者らしい。
地図の研究家、といえば、いまじぶんは今尾恵介氏をおいて右に出る方がいないので、それとは違う視点でしかもそれと同レベルで切らないとなかなかむずかしい。というところで、もうすこしかな。
国土地理院の「紙」の地形図の売り上げが減少しているとのこと。この先どうなるか。
あとがきに、宮脇氏の取材旅行に同行したことがある、とあった。その話のほうが興味あるか。
2008年12月03日 水

★★★★☆
タイトルが「線路観察学」というのはもったいない。
線路(レール)。まくらぎ。ポイントのレールと、転轍する機械(転轍機)。それから、レールの製作現場と、まくらぎ・分岐器の製作現場。さらには操車場と製鉄所の専用鉄道まで。
写真と筆者による詳しい図が多く、機械的な仕組みまで詳しく書かれている。
とてもよい本だ。
2008年11月28日 金

★★★★★(読んでほしい人:自転車に乗る人みんな)
自転車ツーキニストの疋田智氏が渾身の思いを込めて書いた本です。
この国の「自転車」はママチャリレベルでしか取り扱われてこなかった。つまりは、歩道上を歩行者と一緒になって(危険でないスピード=徐行で)走る乗り物だと。
交通法規もそれを前提に「暫定的」「緊急避難的」に歩道上の走行を許していたのだが、いつのまにかそれがデファクトになってしまった。
しかし、自転車を、エコで有効な乗り物にするには、本来のあるべき姿つまり、車道を走行する前提にとらえ直さなければならない。だって、5キロも10キロも走れるためには、そうしなきゃ。
氏が提言するのは、そのために、「自転車は車道を走るべし」「絶対に左側通行を守るべし」だ。
そのために作られた「自転車専用道」ならよいが、エセ自動車専用道(歩道上に線を引いただけ、とか、横断歩道に設けられた自転車横断帯に誘導するとか)を断罪する。
自転車に乗る人は必読の1冊だ
2008年11月28日 金

★★★★☆
蓮見圭一の小説はいい。まだ未読の本があったかと、書店店頭でぱらぱらと冒頭の掌編を見て、読んだことのないものと買い求める。
帰ってから気づく。2年前に読んでいた、と。
〔「心の壁、愛の歌」(2005年刊)の改題増補〕
1作目を増補するとは、上手だな。
2006年6月10日 Sat #085 心の壁、愛の歌
2008年11月21日 金

1年前の本だが、うっかり未読。
「探す」ことに関しては、図書館の果たす役割、というか、図書館こそがその道のプロ、であるべきと思っているのだが、なかなかどうして時代に追い越され、サーチエンジンに負けっぱなし、な昨今。
まだ全体を読み切れていないのだが、「情報探索」モデルに関しても、レファレンスの教科書にでてきたモデルが載っていなくて、その分野の知が生かされていないような気がする。
「レファレンス」と言うよりも「コンシェルジュ」という言葉の方が浸透している昨今。
前にこんな本を読んだ。
2006年9月16日 Sat #137 アンビエント・ファインダビリティ Guro’s Diary
2008年11月20日 木

ふたりで素敵な関係を育てる40のコツ 「意見派」男と「気持ち派」女
以前似たような本を読んだ([post=”482″])が、そのとき読んだ本では、男性側の改善点みたいなものばかり上げられていたが、こちらの本はどちらかというと女性側に立った視点。